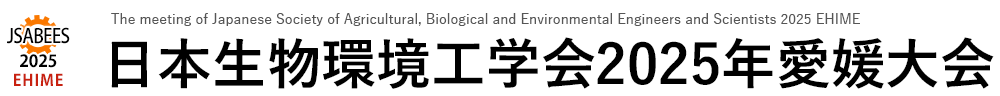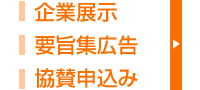市民向け公開シンポジウム
●一般公開シンポジウムⅠ(日本学術会議との共同主催)
Speaking Plant Approach 2.0 ~農業生産現場実装と学術の次なる挑戦~

| 日 時 | 令和7年(2025年)9月16日(火)13:30〜16:00 |
|---|---|
| 会 場 | 愛媛大学農学部 大講義室(〒790-0905 愛媛県松山市樽味3丁目5−7) (オンラインハイブリッド開催) |
| 主 催 | 日本学術会議 食料科学委員会・農学委員会合同 農業情報システム学分科会、 農学委員会 農業生産環境工学分科会、 食料科学委員会・農学委員会合同 CIGR分科会、 日本生物環境工学会 |
| 共 催 | 愛媛大学 |
| 後 援 | 高知大学IoP共創センター、豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター、 (一社)日本施設園芸協会、日本農業気象学会、(一社)農業情報学会、生態工学会、 (一社)農業食料工学会 |
次 第 | 総合司会:藤内 直道(愛媛大学大学院農学研究科 准教授) 13:30 開会の挨拶 後藤 英司(日本学術会議第二部会員、千葉大学大学院園芸学研究院 教授) 13:35 シンポジウム開催趣旨 髙山 弘太郎(日本学術会議第二部会員、豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授・愛媛大学大学院農学研究科 教授) 第一部 SPAの創生と社会実装:農学パラダイムから農業パラダイムへ 司会:林 絵理(日本学術会議連携会員、特定非営利活動法人植物工場研究会 理事長) 13:40 「Speaking Plant Approachの創生と学術研究における展開」 羽藤 堅治(日本学術会議連携会員、愛媛大学 副学長・大学院農学研究科 教授) 13:50 「植物情報を可視化・共有化するInternet of Plants: SPAの多品目・地域展開」 安武 大輔(日本学術会議連携会員、九州大学大学院農学研究院 准教授・高知大学IoP共創センター 特任教授) 岡安 崇史(日本学術会議連携会員、九州大学大学院農学研究院 教授・高知大学IoP共創センター 特任教授) 岩尾 忠重(高知大学IoP共創センター 教授・株式会社高知IoPプラス 代表取締役CTO) 北野 雅治(高知大学IoP共創センター 特任教授・センター長、九州大学 名誉教授) 14:15 「利益最大化CO₂施用を実現するSPAセミクローズド温室」 髙山 弘太郎(日本学術会議第二部会員、豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授・愛媛大学大学院農学研究科 教授) 稲葉 一恵(PLANT CASE株式会社 代表取締役社長・豊橋技術科学大学 研究員) 藤内 直道(愛媛大学大学院農学研究科 准教授) 第二部 SPAの未来:新たな学術領域を牽引 司会:彦坂 晶子(日本学術会議連携会員、千葉大学大学院園芸学研究院 准教授) 14:40 「宇宙農業を支える基盤的技術としてのSPA」 後藤 英司(日本学術会議第二部会員、千葉大学大学院園芸学研究院 教授) 15:05 「デジタルツインにおけるSPA」 福田 弘和(日本学術会議連携会員、大阪公立大学大学院工学研究科 教授) 第三部 パネルディスカッション 15:30 「環境制御型農業生産に貢献するSPA学術研究の展望」 コーディネータ: 髙山 弘太郎(前出) パネリスト: 安武 大輔(前出) 福田 弘和(前出) 林 絵理(前出) 彦坂 晶子(前出) 15:55 閉会の挨拶 仁科 弘重(日本学術会議連携会員、愛媛大学 学長) 16:00 閉会 |
●一般公開シンポジウムⅡ
愛媛県デジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ」における農業DXにおける産官学連携の成果
| 日 時 | 令和7年(2025年)9月17日(水)14:30~16:30 |
|---|---|
| 会 場 | 愛媛大学農学部 大講義室(〒790-0905 愛媛県松山市樽味3丁目5−7) (オンライン ハイブリッド開催) |
| 主 催 | 日本生物環境工学会 |
| 共 催 | 愛媛大学 |
| 後 援 | 日本生物環境工学会 東海・四国支部、日本生物環境工学会生物生体計測部会CIGR(国際農業工学会)Plant factory and intelligent greenhouse WG、豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター、愛媛大学研究協力会スマート農業研究部会、農業情報学会施設生産部会、生態工学会、伊予銀行、愛媛県 |
| 一般参加の可否 | 可(無料) |
| 開催趣旨 | 愛媛県デジタル実装加速化事業、通称「トライアングルエヒメ」は、デジタル・ソリューションと関連技術(AI、IoT、ロボティクスなど)を愛媛県内事業者・自治体等に実装し、地域課題を解決する事業である。農業は重点課題のひとつであり、収益増大や人手不足解消などを目指して生産から消費まで幅広くデジタル化が進められている。面積の4分の3を中山間地域が占める愛媛県では、多様な微気象や土壌条件の中小規模圃場が多い。また、比較的単価の高い果樹・野菜のような園芸作物を中心とした農業生産が展開されていることもあり、そこでの農業生産ノウハウもまた多様である。この多様性をどのような視点からデータ化して活用するかが地域農業のデジタル化・DXにおける成功のカギである。DX利用による急激な温暖化に対策も期待されている。一方で、そのデジタル化のコストは地域農業の経営規模とマッチするものである必要がある。企業が「ビジネスの肌感」を持って主導的に現場課題とデジタル技術のマッチングに取り組み、大学・研究機関が科学的な裏付けの提供とデジタル人材の育成を通じて学術的に支え、県などが技術の社会実装と普及を促進するハブ機能を果たす。この産官学の有機的な連携による収益化可能な計測システムおよび分野横断的なデータ活用を可能とするプラットフォームが今まさに構築されつつあり、デジタル技術の導入が単なる業務効率化にとどまらず地域全体の持続可能な農業エコシステムの形成へとつながっている。本シンポジウムでは、こうした「トライアングルエヒメ」プロジェクトにおける農業DXの具体的な成果や、産官学それぞれの立場からの取り組みを共有し、今後の発展に向けた連携のあり方について議論する。 | 次 第 | (発表タイトルは変更される可能性があります) 総合司会:藤内 直道(愛媛大学大学院農学研究科 准教授) 14:30 開会の挨拶・趣旨説明 羽藤 堅治(日本生物環境工学会 学会長、愛媛大学 地域協働担当副学長、愛媛大学大学院農学研究科 教授) 14:31「トライアングルエヒメ」について 村上 久(愛媛県企画振興部 デジタル戦略局長) 14:35 ブドウ養液栽培+根域制限栽培によるAI化 品川 憲治(ゴールドラッシュ㈱ 代表)・羽藤 堅治(日本生物環境工学会 学会長、愛媛大学 地域協働担当副学長、愛媛大学大学院農学研究科 教授) 15:00 柑橘・サトイモ産地での土壌水分モニタリングによる収益向上 齋藤 透(㈱インターネットイニシアティブ IoTビジネス事業部 副事業部長)・淺海 英記(愛媛県農林水産研究所農業研究部 部長、愛媛県病害虫防除所 所長) 15:25 環境、生体、作業の情報(データ)のデジタル統合による、DXの実現とAI活用可能性の拡大 百津 正樹(㈱アクト・ノード 代表)・和田 博史(愛媛大学大学院農学研究科 教授) 15:50 施設園芸における生体情報モニタリングに基づく環境制御コンサルティングとデジタル人材育成 加納 賢三(㈱デルフィージャパン コンサルタント)・藤内 直道(愛媛大学大学院農学研究科 准教授) 16:15 総合討論 16:25 閉会挨拶 和田 博史(愛媛大学大学院農学研究科 教授) 16:30 閉会 |